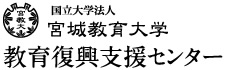�����L�^
2012�N3��13���`30��
��O�������u�Ð쒆�w�Z�Ŋw�������畜���x���������s���܂����B
�������e
�����⏕�A�ۊO�����̕⏕
�Q���w��
3��12�`16���F11���i���k�w�@��w�S���A���s�����w�V���j


2012�N3��5���`16��
��������������ꏬ�w�Z�Ŋw�������畜���x���������s���܂����B
�������e
�����⏕
�Q���w��
3��5���`9���F13���i�Q�n��w7���j


�Q���w��
3��12���`16���F10���i�ޗNj����w10���j


2012�N3��4��
���ʎx������t�H�[�������J�Â��܂����B
2011�N3��11���̓����{��k�ЂƑ�Ôg�A������_�@�Ƃ��Ă͂��܂������܂��܂ȋ��́A�ˑR�Ƃ��Ď������ɍ���Ɖ������ׂ��ۑ��˂��t���Ă��܂��B
���̈���ŁA��N���o�߂��悤�Ƃ��邱�Ƃ̎������ЂƂ̋��Ƃ��āA���̊Ԃ̋ꂵ����U��Ԃ�A���̌o�����E���͂��A����܂Ō��߂�����Ă�����X�̖��_��o���ƂƂ��ɁA����̂��܂��܂ȃV�X�e���\�z�ɖ𗧂Ă悤�Ƃ��铮���������n�߂Ă��܂��B
����̃t�H�[�����́A�k�Ђɒ��ʂ������ʎx������̌���Ǝx���҂̎��_����A�����{��k�Ђ̌o�����E���́E�𗬂��A���ʎx������Ɍg���҂̍���̊����ɕ�������^����c�_�W�J�����҂�����̂ł��B

- �Q���Ώ����E�����A��ʎs��
- �����@ ���i13���`�j
�A �J��i13��30���j
�B ��Î҂������i�{�鋳���w���A���ʎx�����瑍�������Z���^�[���j
�C �V���|�W�E���F�u�����{��k�Ёv�Ɠ��ʎx������i13��40���`�j
�e�[�}�ݒ�i13��40���`�j
�E�{�l���猩�����u�k�Ёv�ɂ�����x���Ƃ��̉ۑ�F����R���i�{�鋳���w�j
�E��Вn�̎x���w�Z�́u�x���v�Ɩ{�w�̖����F����T�s�i�{�鋳���w�j
�b��T�i14���`�j
�E�ЊQ�Ɠ��ʎx���F���ԉp���i���s�����w�j
�E�S���̎x���w�Z�̔�ЏF���q����i�������ʎx�����瑍���������j
�b��U�i15��10���`�j
�E�{�錧���̓��ʎx���w�Z�̔�ЏƂ���ւ̑Ή��F
����a���i�{�錧���ʎx�����猤�����E�{�鋳���w�������ʎx���w�Z���Z���j
�E��Вn�̊w�Z���猩�����ۑ�F�N�c���i�{�錧���Ί��x���w�Z�Z���j
���_�Ƒ����i15��40���`�j
�D ��i16��35���`�j
���ʎx������t�H�[�����@�|�X�^�[
20120304_symposium.pdf
2012�N1��13�`15��
�X�`���[�f���c�E���r���h�@�܂�߃v���W�F�N�g
�`�ɂ�����ς���ƁE���肪�Ƃ����������Ɂ`�@�̃C�x���g�Ɋw�����Q�����܂����B
- ��|���E�̎q���������A��H��H�S�����߂Đ܂�ꂽ�܂�߂��g�p�����I�u�W�F�E���[�N�V���b�v��ʂ��ē��k�̎q�������ƑS�Ă̎q�������E���E�̎q�������Ƃ��i���q���ł��������B
�܂��A�o�����������I�u�W�F�����w�Z�E�����قȂǂ̎q���̊֘A�{�݂ɐݒu���邱�ƂŁA��Ђ��ꂽ�n��̊F�����A���{�̎q�������Ɛ��E�̎q�������Ƃ��J�ɂ��ĉi���q���ōs�����Ƃ�ړI�E��|�Ƃ��鎖�Ƃł��B - �J�Ïꏊ�G�X�p�����F1�E�X�N�G�A
- �J����1��13���i���j�@10:15�`�@�I�[�v�j���O�Z�����j�[
14���i�y�j�@10:00�`16:00�@��ʖ����Q�����[�N�V���b�v
15���i���j�@10:00�`16:00�@��ʖ����Q�����[�N�V���b�v
16:00�`21:00�@���E�n�}�ق��̃I�u�W�F�W���@21:00�I��
��3���Ԃ̃��[�N�V���b�v�Ő��삳�ꂽ�I�u�W�F�Ȃǂ́A���[�N�V���b�v�̏I����A�ȉ��̏ꏊ�ɓW���\��ł��B
�E�։����w�Z
�E����Ԓ����w�Z
�E�����s���Z���^�[
�E�K��������


�X�`���[�f���c�E���r���h�@�܂�߃v���W�F�N�g�@�|�X�^�[
20120113_orizuru.pdf
�J�ÏI���̂���
1��13���`15���J�Ê��Ԃ�1500���قǂ��Q�����܂����B
���[�N�V���b�v�J�Âɂ�����{�鋳���w�A���k����������w�A���k�|�p�H�w�ȑ�w�@�e�w���{�����e�B�A�v38���̂����͂ƞ։����w�Z�A����Ԓ����w�Z�̐��k�ق���R�̕��X�̎Q�������͂������A���E38�J���̎q����������̐܂�߂ɍ��߂�ꂽ�v���𓌖k�̎q�������Ɍq�����Ƃ��ł��܂����B
�Q���w���̐�
-
�c�t����ۈ牀�ɒʂ��悤�Ȏq�����珬�w�Z��w�N���炢�܂ł̎q�ǂ��������������Ă���܂����B
�u���R�ɑ��������Ă�����B�v�ƌ����ƁA�Y�݂Ȃ�����y�������ɒ߂��l�߁A�V�[����\��p����ۓI�ł����B�q�ǂ�������l�ЂƂ�̌������Ɍ���Ă��Ėʔ����ȂƊ����܂����B
���͂܂�����قǏڂ����͂���܂��A�����Ǝq�ǂ��̏W�܂�Ƃ����c�t���A�ۈ牀�̊����̈�тƂ��čs���A��������̎q�ǂ������ɎQ�����Ă��炢�����Ǝv���܂����B
�܂����̂悤�ȃ{�����e�B�A������܂�����Q�������Ă������������ł��B���肪�Ƃ��������܂����B -
�����Ȋ��z�Ƃ��āu����Ă悩�����v�ƐS����v����{�����e�B�A�ł����B
����܂ŗl�X�ȃ{�����e�B�A�Ɋւ���Ă��܂������A����قǂ܂łɏd�݂̂���{�����e�B�A�͍����߂Ăł����B�������̓I�Ɍ����ƁA���ɗ������鏬�w���̒j�̎q�̈ꌾ�ɏW���Ǝv���܂��B���̈ꌾ�Ƃ́A�u��Вn�̐l�ɂ��F�肵�Ȃ���v�Ƃ����ꌾ�ł����B
���̎q�͒߂̐��E�n�}���쐬����ہA��H�̒߂�u�����Ƃɂ��F������Ă��܂����B
�����A�u���ł��F������Ă���́v�ƕ����ƁA�ނ́u��Вn�ł͂܂��ꂵ��ł���l���������邩��A������������悤�ɂ��肢���Ă����v�Ɠ����܂����B
���̂Ƃ��A���͂͂��Ƃ��܂����B���݂̎��̓���͉��̕s���R���Ȃ������ł��Ă���̂ɁA���������ɂ͂܂��܂��ꂵ��ł���l���吨���邱�Ƃ�Y�ꂩ���Ă��邱�ƂɋC�Â�����܂����B���������Ӗ��ŁA����̃��[�N�V���b�v��ʂ��āA�����{��k�Ђł͐��E���̐l�X���x�������Ă��ꂽ���ƁA�܂��A�����Ɍ����Ĉꐶ�����������Ă���Ă��邱�Ƃ����߂Ċ����邱�Ƃ��ł��܂������A����𑽂��̐l�B�ɍL�߂�ꂽ���Ƃ͂ƂĂ��Ӗ��̂��邱�Ƃ��Ǝv���܂����B
�����A�{��Ő��܂������҂Ƃ��Ă��̂��Ƃ��������A���p���ł����g��������Ǝv���܂��B
����������Ƃ邱�Ƃ��ł��������ł��A�������g�{���ɂ悩�����Ǝv���܂����A���ꂩ��������ɂł��邱�Ƃ�����ΐϋɓI�ɋ��͂��Ă��������ł��B